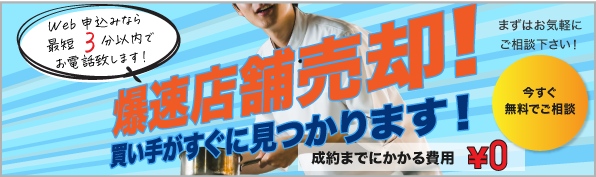店舗物件を借りる際に必要となる初期費用の中で、大部分を占める保証金ですが保証金は何のために存在してどんな役割を持っているのかご存知でしょうか。
この記事では、テナントの保証金とは何なのかをはじめ、保証金と敷金の違いや保証金の相場、保証金は返金されるのか、把握しておくと良いポイントについて解説します。
テナントの保証金とは?
テナントの保証金とは、店舗物件を契約する際に賃料などの債務の担保や原状回復工事のための費用として貸主や管理会社に預ける費用です。
原状回復の費用に充てられる可能性があることから、スケルトン物件のような入居時に工事が必要な物件は保証金が高くなる傾向にあります。
退去時は、滞納した賃料の不足分や原状回復にかかる費用などを差し引いて返金されます。
保証金と敷金の違い
保証金と敷金の用途は同じで、どちらも物件を利用する期間中に発生する様々なリスクに備えるために貸主に預ける費用です。
敷金の場合、物件の借主の故意・不注意による汚染・毀損がある場合を除いては全額返金されるケースが多いです。
保証金の場合は、預けた費用から「償却分」を無条件に差し引かれるケースがほとんどです。
テナントの保証金の相場
テナントの保証金は物件によって異なりますが、賃料6〜10ヶ月分が相場です。
ただし、繁華街や駅前などの人気エリアのテナントの場合、2年分の賃料を保証金として設定している場合もあります。
賃料が20万円のテナント物件の場合、保証金は120〜200万円となります。
物件を探す際には、物件の広さや内装の良さ、賃料以外にも保証金が賃料の何ヶ月分必要なのかよく確認しましょう。
テナント物件の保証金は返ってくる?
テナント物件の保証金は原則として退去時に返金されますが、保証金から償却費・原状回復工事費用を賄う契約の場合、減額されて返金される場合があります。原状回復工事にかかる費用によっては、追加費用が発生するケースも少なくないです。
また、テナント物件の保証金は賃貸契約終了後から日数を計算して返金されるため、退去後に物件を利用していない時期があったとしても、契約上では賃貸契約が残っていると保証金は返金されませんので注意しましょう。
引かれる費用(償却費用、減少する例)については、後述しますのでご一読ください。
保証金に消費税はかかる?
保証金や敷金は、返金が原則の預かり金に該当するため消費税は非課税となります。
ですが、保証金償却など保証金・敷金のうち借主に返金を要しないものは物件を賃貸したことの対価となり、事業用資産として扱われるため消費税課税対象となりますので注意しましょう。
保証金は償却される
保証金償却とは、テナント物件に入る際に最初に預けた保証金が一定の割合で減少していくことを指します。
償却の記載には一般的に
・解約時償却2ヶ月
・保証金の償却年10%
この2種類のパターンがあります。
解約時償却2ヶ月と記載されている場合は、賃貸借契約の解約時に保証金の2ヶ月分が解約時に差し引かれて返金されます。
保証金の償却年10%と記載されている場合は、1年ごとに10%保証金が償却されて返金されます。
保証金の償却に関しては賃貸借契約書の特約事項として記載されているので必ず確認しましょう。
「償却」とは?
「償却」とは、保証金が返金される際に一定額を差し引くことを指します。
保証金は預り金のため消費税非課税ですが、償却は消費税課税対象となり、償却費に適用税率を掛けた金額が保証金から差し引かれます。そして、契約内容によっては、入居期間が短いと償却費が高くなる場合がありますので注意しましょう。
償却費の相場
一般的な償却費の相場は、保証金の10〜20%もしくは、敷金の賃料の1〜2ヶ月分程度ですが、償却率をあらかじめ設定し契約期間に応じて償却されるという契約もあります。
償却費は、保証金 × 償却率 ×テナント 物件使用年数 = 償却費という方法で計算されます。
保証金を200万円預けていて、償却率が10%、テナント物件の使用年数が5年の場合は、
例:保証金200万円 × 償却率10% × テナント物件使用年数5年=償却費100万円
となり、保証金の償却費が100万円ということになります。
保証金の返金額が減る要因
保証金の返金額が減る理由は主に以下の3つです。
・償却分が差し引かれる
・賃料や光熱費の滞納・未払い
・原状回復工事の欠陥
この3つの要因は保証金を返金される際にトラブルになりやすい代表的なものです。
ここでは、保証金の返金額が減る要因についてそれぞれ解説します。
償却分が差し引かれる
保証金の返金額が減る要因の一つに償却分が差し引かれるというものがあります。
賃貸借契約書に「退去時に10%の償却」や「毎年10%償却」と特記事項に記載されている場合は、償却分が差し引かれますので、契約書を必ず確認しましょう。
賃料や光熱費の滞納・未払い
物件の契約期間中に何かトラブルが発生した時の備えとして貸主に預ける保証金ですが、賃料や光熱費の滞納や未払いがあった場合は、保証金から差し引かれるため返金される金額が少なくなります。
そうならないためにも、帳簿をつけるなど支払っていない期間の記録を必ず取るようにしましょう。記録を取ることで、後々トラブルを回避する証拠になります。
原状回復工事が不十分
賃貸借契約書に記載されている原状回復工事やスケルトンに戻す工事内容と、実際の原状回復工事に相違があり、工事が不十分と判断された場合は、保証金から原状回復工事費用を差し引かれることがあります。
例:物件の壁や床を張り替えて返却しなければならないところを、工事をせずに返却した場合
この場合、貸主や管理会社は、もう一度物件の原状回復工事をしなければなりません。
その結果、原状回復にかかる費用を差し引かれる場合がありますので注意しましょう。
保証金を減額するためのポイント
保証金を減額するためのポイントの一例は以下の通りです。
・周辺地域で似た物件の保証金相場と比較し交渉
・保証会社の利用
保証金は物件契約時の初期費用の大部分を占めるため、減額できると大きな経済的メリットとなります。
それぞれ解説します。
周辺地域で似た物件の保証金相場と比較し交渉
入居を検討しているテナントが周辺地域の似た物件の保証金相場より高い場合は、交渉することが可能です。交渉する場合は、単純に安くして欲しいと言うより、賃料や契約期間、賃貸条件など貸主にとってメリットが生じる内容を提示すると良いでしょう。
ただし、賃貸借契約を交わしたのちに減額交渉することや、競合の入居希望者がいる場合、人気の物件の場合は交渉できませんので注意しましょう。
保証会社の利用
保証金を減額するために保証会社を利用することを検討してみるのも良いでしょう。
保証会社の審査に通過することで、保証金の減額や免除が可能となります。
保証金を減額することができると、
・物件の内装費用
・人件費
・備品や什器の購入
・事業の投資・拡大
など店舗やオフィスの運営に関わる重要なところに費用を充てることができます。
保証会社を利用する場合は、貸主や管理会社が指定している保証会社があるのか、保証会社のサービス内容の詳細や条件をしっかりと確認することが重要です。
まとめ|テナント物件の保証金には様々な制約があるので気を付けましょう
テナント物件の保証金は、初期費用の中でも大部分を占める費用のひとつで高額になることも多いです。保証金は敷金と違い、「償却分」が差し引かれて返金されたり、賃料や光熱費の滞納・未払い分や原状回復費が差し引かれた分が返金されるといったトラブルが発生しやすいなど、様々な制約があります。
事前に保証金についての注意点やポイントを理解・把握しておくと、後々のトラブルを回避できるので、物件を契約する際は十分に確認することが大切です。