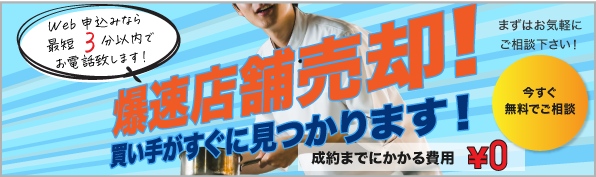店舗やオフィスを開業するために行うテナント物件の工事ですが、業者の選定や発注、費用負担は誰が行うのかを区分したものを「A工事」・「B工事」・「C工事」というものに分けられます。
今回は、テナント物件の工事とは何かをはじめ、A工事・B工事・C工事の区分と事例、テナント物件の工事をする際に挨拶やお知らせが必要か否か、確認申請手続きについて解説します。
テナント物件の工事とは
テナント物件の工事とは、借主が物件を利用するために、内装工事を施して空間を改装したり、必要な設備や機器を設置することを指します。通常、新しい店舗、事務所、飲食店等のビジネスを開始する際に施工されます。
一般的にテナント物件の工事はA工事・B工事・C工事の3つの工事区分に分類され、業者の発注や選定、費用負担を誰が行うかによって名称が異なります。
以下で詳しく解説します。
A工事・B工事・C工事の区分と事例
テナント物件の工事にはA工事、B工事、C工事の3つの区分があります。
それぞれの工事事業者の指定・発注、費用負担者は表の通りです。
| A工事 | B工事 | C工事 | |
| 業者の選定 | オーナー | オーナー | テナント |
| 業者の発注 | オーナー | オーナー | テナント |
| 費用負担者 | オーナー | テナント | テナント |
・A工事
工事業者の発注、選定、費用負担の全てがオーナーの責任で行われる工事区分で、建物の構造(壁・柱・看板・共用部・梁など)に関わる工事が該当します。
・B工事
工事業者の選定と発注はオーナーの責任にて行いますが、費用についてはテナント側の責任で負担するという工事区分で、専有部内にある建物全体に影響する設備の工事が該当します。
・C工事
工事業者の発注、選定、費用負担の全てがテナントの責任で行われる工事区分で、テナント物件に起因する什器・備品の設置・作成・内装の造作が該当します。
また、以上の工事の事例について解説します。
A工事:共用部
A工事とは、建物の資産価値を維持するために行われる工事を指します。
工事箇所は、建物の外装や外壁、共用通路、エレベーター、共用トイレなどの躯体や共用の設備等が該当します。
B工事:防災・空調設備等
B工事とは、専有部分ではありますが建物全体に関わる部分の工事で、テナントの希望で行われる工事を指します。
工事箇所は、防災・空調設備、分電盤、衛生設備等が該当します。
B工事は、オーナーが選定した業者に依頼しますが費用はテナント側の負担であるため、テナントはオーナーに費用の交渉をすることとなります。
C工事:内装
C工事とは、内装工事のうち建物全体の安全性に影響しないものを指します。
C工事はA、B工事とは異なり工事業者をテナント側で選定するため、複数の業者で相見積もりを取り、費用を比較することが可能です。
スケルトン工事・原状回復工事との違い
一般的にA工事・B工事・C工事と、 スケルトン工事・原状回復工事は別の工事を意味します。
スケルトン工事とは、床や天井、内部の造作だけでなく、什器、衛生設備、電気配線を全て解体し竣工時の骨組みだけの状態にする工事です。
一方、原状回復工事とは、退去時に入居前の状態に戻す工事を意味します。
契約内容によって異なりますが、スケルトン工事のことを指す場合もあります。一般的にはテナント側の都合で設置・造作した什器、備品、内装を解体し、契約終了までに入居前の状態に戻す必要があります。
テナント物件の内装工事・費用
テナント物件の内装工事とは、貸室に付随する設備・床・壁紙の張り替え等の内装工事、什器備品、コンセントやブレーカー、照明器具の増設、専有部の配線工事など、主に専有部内の工事が該当します。
以下の内容について詳しく解説します。
・内装工事費用
・勘定科目
・耐用年数
テナント物件の内装工事で発生する内装工事費用は高額な固定資産と扱われ、会計処理の際に勘定科目と耐用年数を使用して減価償却を行います。
以下でそれぞれ解説します。
テナント物件の内装工事費用
テナント物件の内装工事費用は、坪単価から算出でき、およそ30万〜50万円が相場といわれています。坪単価に内装工事をするテナント物件の延べ床面積を掛けることで予算のイメージが可能です。
例えば、内装工事を計画しているテナント物件の坪単価が30万円で、延べ床面積が10坪の場合の内装工事費用の算出方法は、
30万円 × 10坪=300万円
となります。
ただし、業種・業態によっては単価と異なる場合もありますので注意しましょう。
勘定科目
テナント物件の内装工事の会計処理は「建物付属設備」「建物」「諸経費」「備品」の4つの勘定科目に仕訳されます。
防水工事、ガラス工事、木工工事、造作工事のような建物に固定されている部分の内装工事の勘定科目は「建物」として仕訳します。一方で、ガス設備、空調設備、電気設備、防災設備、自動開閉設備は、建物の使用価値を増加させたり、建物を維持させるものに関する勘定科目は「建物付属設備」として仕訳します。
そして、工事に必要な手続きで発生した手数料や人件費等は工事の際に間接的に発生する経費に該当するため、「諸経費」として仕訳します。
また、パソコン、電話、机、椅子等は業務を行う際に必要な消耗品に該当するため、「備品」として仕訳しますが、壁や床に設置できて、尚且つ20万円以上でないと備品として仕訳できませんので注意しましょう。
耐用年数
耐用年数は、減価償却資産を使用することができる年数のことです。減価償却資産がどの年数で資産価値が消滅するのかを表したもので、この耐用年数をもとに減価償却の会計処理をします。
テナント物件の内装工事の勘定科目は「建物」に該当するため、耐用年数にあわせて減価償却をする必要があるため注意しましょう。
テナント物件の工事をする場合、挨拶やお知らせは必要?
テナント物件の工事をする際、挨拶やお知らせは必要かどうか悩む方も多いでしょう。
結論から言うと、工事を円滑に行うためにも周辺への挨拶やお知らせは必要です。
ここでは、工事の挨拶やお知らせのタイミング、工事前に行政に申請する書類について解説していきます。
工事の挨拶やお知らせのタイミング
テナント物件の工事の挨拶やお知らせのタイミングは、着工前の10日から1週間前に行うのがベストです。 なぜなら、テナント物件が多いエリアだと各テナントによって休日が異なる可能性があるからです。
また、周辺の各テナントに挨拶やお知らせをする際は、営業前・アイドルタイム・営業終了後など他テナントの営業に影響を及ぼさない時間帯を選びましょう。
出店エリアが住宅地の場合は、土・日・祝日の夕方や明るいうちに挨拶に行くのをおすすめします。
「確認申請」の注意点
テナント工事を進める前に行政への確認申請手続きが必要な工事項目があるのをご存知でしょうか。
確認申請が必要な項目は、建物の主要構造部である壁、柱、床、梁(はり)、屋根、階段を半分以上修繕もしくは模様替えをする場合です。これは例え新築でない場合でも確認申請が必要になります。
ただ、テナント側が行う「確認申請」は、保健所と消防が主であり、行政への確認申請は自治体によりますので、ご自身の自治体で確認を行いましょう。
まとめ|工事区分を確認しましょう
テナント工事は業者の発注や選定、費用負担を誰が行うのかによりA工事・B工事・C工事の3つの工事区分に分類されます。この3つの工事区分をしっかりと理解することで、事前にトラブルを予防することが可能です。
それぞれの工事内容は契約書に記載されている「工事区分表」で確認することができますので、一度目を通しておくと良いでしょう。
また、テナント工事前に挨拶やお知らせをすることで円滑に工事を行うことができるため、周辺への挨拶やお知らせ、行政への確認申請を忘れずに行いましょう。