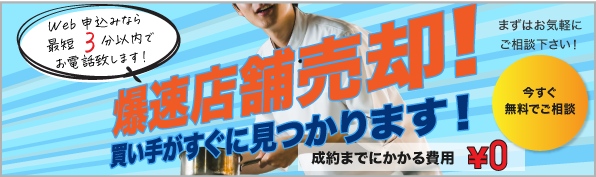店舗やオフィスを経営するために契約するテナント契約ですが、「テナントの契約期間に規定はあるのか?」「やむを得ない事情で中途解約ができるのか?」「中途解約をする際の解約予告はいつまでにするのか?」と悩んでいる方もいるでしょう。
この記事では、テナントの契約期間をはじめ、普通借家契約と定期借家契約の各契約形態の違いや、各契約形態の中途解約や解約予告期間について解説します。
テナントの契約期間とは?
テナントの契約期間とは、契約で定められている物件を借りられる期間のことです。
契約形態や内容によって具体的な期間は異なりますが、一般的なテナントの契約期間は2〜3年が多いです。
数ヶ月でテナント退去の必要が出てきた際は、中途解約となります。一般的にテナント退去の際は、退去予定の3〜6ヶ月前に退去予告を伝える必要がありますので注意しましょう。
契約期間は契約形態で異なる!?
テナント契約の契約期間は契約形態で異なります。
普通借家契約の場合は、契約期間が2〜3年程度になることが一般的で、物件の貸主に正当な理由がない限り、賃貸借契約は自動的に更新されます。
一方で、定期借家契約は契約期間が定められており、「自動更新」はされない契約形態となります。定期借家契約で契約満了後も借りたい場合は「再契約」を行う必要があります。
「普通借家契約」と「定期借家契約」
「普通借家契約」と「定期借家契約」の各契約形態の違いは以下の通りです。
| 普通借家契約 | 定期借家契約 | |
| 契約期間 | 1年以上(1年未満は期間の 定めがない賃貸借契約となる) | 制限なし |
| 更新の有無 | 契約満了時に契約期間の 更新可能 | 契約期間満了後に終了 (基本的に更新不可。再度契約 すれば利用できる可能性はある) |
| 更新料 | あり(基本的には契約更新時に、家賃一か月相当を支払う必要がある) | なし。 再契約を行う場合は「再契約料」を支払う可能性がある。 |
| 中途解約 | 契約内容に従う | 原則は不可(特約に従う) |
| 賃料の交渉 | 可能 | 可能 |
※特約:契約書の条文に当てはまらないテナント特有の取り決めのこと。
テナント契約には「普通借家契約」と「定期借家契約」の契約形態があります。
普通借家契約は一般的な契約形態で、定められた契約期間満了の際に契約更新料を支払うことで、賃貸契約を更新できる契約です。
一方、定期借家契約は貸主側が定めた契約期間満了とともに、”必ず契約が終了する”といった、借主の権利に一部制限がかかってしまう契約形態です。
物件によって契約形態や契約期間が変わるため、必ず契約期間をチェックしましょう。
「普通借家契約」の中途解約
普通借家契約では、テナントの借主による解約はいつでも行えますが、貸主による解約の場合は解約の6ヶ月前に予告すること、そして解約するための「正当事由」が必要となります。
「貸主の自己使用」、「物件の老朽化による建替え」、「敷地の有効利用、高度利用」が認められる場合には、中途解約金を支払うことで正当事由が認められるケースが多いです。
テナントの解約予告期間
テナントの解約予告期間は契約内容によって異なりますが、解約の3〜6ヶ月前の告知を求められるケースが多く、解約予告期間中の賃料は解約まで支払う義務があります。
また、貸主による解約の場合は、解約申し入れから6ヶ月後にテナント契約が終了することになります。
中途解約金の相場
普通借家契約の中途解約金の相場は、賃料1ヶ月〜2ヶ月分程度です。
契約書には、「1年未満の解約の場合は賃料1ヶ月分」や「半年未満の解約の場合は賃料の2ヶ月分」、「2年未満の解約の場合は賃料1ヶ月分」といった条件で記載されている場合が多いです。
「定期借家契約」で中途解約できる3つのケース
定期借家契約は基本的には中途解約できませんが、場合によっては中途解約が可能です。
「定期借家契約」で中途解約できる3つのケースは以下の通りです。
・解約権留保特約を使用する場合
・中途解約権が行使できる場合
・違約金を支払う
以下でそれぞれ解説します。
解約権留保特約を使用する場合
解約権留保特約とは、契約期間内での中途解約を認める条項のことです。
契約書に解約権留保特約の記載があれば、定期借家契約期間中であっても中途解約の申し入れができます。
事情があり定期借家契約を中途解約したい場合は、契約書に解約権留保特約の記載がないか確認しましょう。
中途解約権が行使できる場合
定期借家契約時に解約権留保特約を締結していなかった場合でも、中途解約権を行使することで中途解約できる場合があります。
中途解約権の行使をする際は、以下の3つの条件を満たす必要があります。
1.居住目的で物件を使用している場合(事業目的でも事業用店舗と住宅兼用の場合は例外)
事業用店舗の場合は中途解約権を行使することはできません。
ただし、事業用店舗と住宅を兼用している場合は、中途解約権の行使が認められます。
2.物件の床面積が200平方メートル未満の場合
事業用店舗と住宅兼用物件の場合は、店舗部分も含めた全体の床面積が200平米未満である場合は中途解約権の行使ができます。
3.やむを得ない事情によって契約続行が困難になった場合
やむを得ない事情で、物件の契約続行が困難であると判断された場合も、中途解約権の行使が認められます。
やむを得ない事情とは、「病気を罹患してしまい療養が必要になった」「転勤を命じられて引っ越すことになった」「親族の介護をすることになった」といった場合です。
「物件を借りる時点において、予測することができない事態」に該当するものが対象ですが、やむを得ない事情には明確な定義がないため、貸主や弁護士、裁判所の判断に委ねられます。
以上3つの条件を満たせば、貸主に対して中途解約を申し入れることができます。
契約書に「中途解約を認定しない」と記載があった場合でも、解約の申し入れから1ヶ月が経過することで解約が成立します。
違約金を支払う
定期借家契約期間中に中途解約する場合は、違約金が発生することが多いです。
違約金の金額は契約書の内容によって異なりますが、賃料や共益費等の半年から1年分相当が目安となります。
例えば、契約期間が半年残っている場合、半年分の賃料を支払うことで中途解約が可能です。
解約権留保特約や中途解約権を行使するのが難しい場合は、残りの賃料相当分のお金を用意して中途解約の申し入れをしましょう。
まとめ|契約期間はきちんと確認しましょう
テナント契約は、普通借家契約と定期借家契約の2つの契約形態に分類されます。
この2つの契約形態や中途解約についてしっかりと理解しておくことで、解約時のトラブルにも巻き込まれにくくなります。
普通借家契約は自動更新されるのに対し、定期借家契約は貸主側が定めた契約期間内のみ契約が発生し、契約期間満了時に契約が終了しますので各契約形態の契約期間はしっかりと確認しましょう。