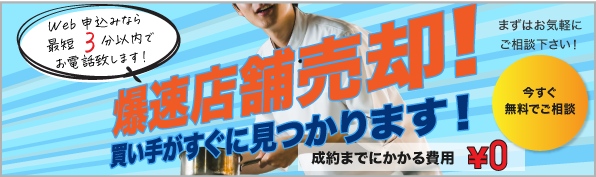テナントの賃貸ビルを経営していると、「事情がありテナントを退去させたい」「テナントの立ち退き交渉を円滑に行いたい」「立ち退き交渉の進め方を知りたい」と考えている方もいるのではないでしょうか。
借主側が納得できる交渉を行わないと、裁判に発展し様々なスケジュールに支障が出てしまう可能性があります。
この記事では、テナントの立ち退きは何かをはじめ、立ち退きが認められる正当事由から立ち退きの判例、立ち退き料の相場についてご紹介します。
立ち退きとは?立ち退きが認められる正当事由
テナントの立ち退きとは、賃貸借契約に基づき、オーナー(貸主)が建物の老朽化や都市再開発のために建て替えや取り壊し、テナントの自己使用が必要になったなどの理由で、借主に対して、契約更新の拒否や解約の申し入れを行い、テナントからの退去を請求することをいいます。
テナントの立ち退きが認められるのは、借地借家法に基づいた正当事由であることが条件になります。
正当事由とは、以下の事由を考慮して決定されます。
①建物の老朽化
②土地の再開発
③オーナーによる自己使用
④テナントの過失行為
以下で詳しく解説します。
①建物の老朽化
建物の老朽化によりテナントの立ち退きを求められる際の主な理由は以下の通りです。
・災害時の安全性の確保
経年劣化により老朽化した建物は、構造上の耐震性や構造強度が低下している可能性があり、地震や火災等の災害時に安全性を確保できないというリスクが発生します。
そのため、借主の安全を確保するためにテナントの立ち退きを求めることがあります。
・建物が著しく老朽化しており修繕や改修が困難
建物が著しく老朽化している場合、修繕や改修が困難なケースがあります。
このような場合は、建物の修繕にかかる工事費用が高額になるため、建物の取り壊しや建て直しが検討され、テナントに立ち退きを求めることがあります。
②土地の再開発
再開発は、地域全体の価値を向上させるために都市の機能向上や土地の有効利用を目的として計画されるものです。
再開発は、地域全体の発展や安全性の向上に寄与するため、場合によっては正当な事由に該当します。
土地の再開発によりテナントの立ち退きを求められる際の主な理由は以下の通りです。
・土地の有効活用と収益性の向上
都市再開発は、土地を有効活用して商業施設、オフィスビル、住宅などの新しい用途に転用して地域全体の経済効果を高めるために計画されるものです。
そのため、都市再開発に適さない建物を取り壊して新しい建物を建設するために、テナントに退去を求めることがあります。
・公共施設の整備やインフラの改善
都市再開発には、地域の利便性向上や防災対策のための道路の拡張や公共施設の整備、インフラの改善も含まれるため、工事に伴ってテナントの立ち退きを求めることがあります。
このような理由から、土地の再開発によりテナントの立ち退きを求められることがあります。
③オーナーによる自己使用
オーナーによる自己使用によりテナントの立ち退きを求められる際の主な理由は以下の通りです。
・オーナーが個人的に使用する
「オーナーが家族と居住するための住宅として使用する」または「オフィスや店舗としてオーナー自身がビジネスを始める」など、自己使用を目的として建物を使用したい場合、テナントに立ち退きを求めることがあります。
・オーナー自身の事業拡大や新規事業の開拓
オーナー自身の会社の事業拡大や新規事業の開拓により建物を使用したい場合、オーナー自身の会社のオフィスや店舗に転用するなどの目的として、テナントに立ち退きを求めることがあります。
・生活の変化による建物の改装やリノベーション
オーナーの生活環境の変化や健康上の理由から、オーナーが所有している物件に移り住む事を考えている場合や、建物の改装やリノベーションを行った後、自己使用する計画がある場合、テナントに立ち退きを求めることがあります。
このような理由から、オーナーの自己使用によりテナントに立ち退きを求めることがあります。
ただし、オーナーの自己使用を理由に立ち退きを求める場合、賃貸借契約法の規定に基づいて、テナントとの合意や適切な通知を行う必要があります。
また、場合によっては借主に立ち退き料を支払うなどの補償が求められることもあります。
④テナントの過失行為
テナントが過失行為を犯した場合に立ち退きを求められる際の主な理由は以下の通りです。
・賃貸契約の違反
テナントが「オーナーの許可なく第三者にテナントを転貸した」、「契約で禁止されている事業を行なった」などの賃貸契約内容に違反する行為をした場合、契約違反とみなされ、オーナーからテナントの立ち退きを求められることがあります。
・賃料の未払い
テナントが賃料を長期間滞納した場合、契約上の義務違反とみなされ、オーナーから契約解除され、テナントの立ち退きを求められることがあります。
・建物や設備の損壊
テナントが故意または過失により室内の無断改造、放火や重大な事故による損壊などにより建物や設備を損壊した場合、契約違反とみなされ、オーナーからテナントの立ち退きを求められることがあります。
・迷惑行為や違法行為の発生
テナントが騒音や違法活動などにより、他のテナントや近隣住民に迷惑をかける行為を繰り返す場合や、違法な薬物の売買や使用、許可無しで風俗を営業するなどの法律に反する行為が発生した場合、オーナーがテナントの行動が正常な建物運営を妨げると判断され、賃貸契約の解除やテナントの立ち退きを求められることがあります。
立ち退きが認められた判例
立ち退きが認められた判例は、以下の通りです。
・判例1:築年数53年経過した建物の老朽化による雨漏りで完全な修理ができず立ち退きを求めた事案
・判例2:築年数45年経過した建物の老朽化により建物の耐震性に問題があり立ち退きを求めた事案
以下で詳しく解説します。
判例1:高齢で障がいを持つ家主の生活空間確保の必要性から立ち退きを求めた事案
二階に自宅を構える高齢かつ身体に障がいを持つ家主が、一階で焼き鳥店を経営するテナントに対し、物件からの退去を要求。 家主は、常に介護を必要とする状態で、他に居住できる場所がなく、二階部分だけでは家主と介護者の生活空間として手狭であり、日常生活を送ることが困難な状況でした。
テナントが物件を使用する緊急性よりも、家主が建物全体を利用する緊急性の方が高いと判断されました。 従って、裁判所は焼き鳥店に物件からの退去命令を下しました。
テナントは改装などを行っておらず、工事費などの支出がほとんど認められませんでした。 180万円の立ち退き料の支払いを条件とした退去は、妥当であると判断されました。
>>参照元:焼き鳥店の立ち退き事案
判例2:築年数45年経過した建物の老朽化により建物の耐震性に問題があり立ち退きを求めた事案
公認会計士・税理士事務所が入居していた建物は、築年数45年が経過しており、耐震性の調査を行った結果、震度6や震度7の地震が発生した場合、建物が大きく損壊するまたは完全に崩壊するという調査結果があり、耐震性を上げるために耐震補強費用として5,000万円以上かかる可能性があり、貸主側に対して立ち退きを求めました。
このケースでは、現在借りている建物での営業を必ずしも継続する必要性が低く、立ち退きを求めることは正当な事由であると判断されました。
立ち退き料に関しては、貸主側が不動産鑑定を行った442万円の評価額を採用し、立ち退き料を38万円増額した500万円を支払うことを命じました。
>> 参照元:公認会計士事務所の立ち退き事案
立ち退きが認められなかった判例
立ち退きが認められなかった判例は、以下の通りです。
・判例1:貸主側の息子夫婦の付き添い看護を受ける必要性に伴う立ち退き事案
・判例2:建物の経年劣化によるビル建築のための取り壊しの必要性に伴う立ち退き事案
以下で詳しく解説します。
判例1:貸主側の息子夫婦の付き添い看護を受ける必要性に伴う立ち退き事案
貸主側が建物で息子夫婦の付き添い看護を受ける必要があるとして、借主側に対して解約を申し入れました。
このケースでは、現住居を有効に活用することで息子夫婦との同居が可能である一方、借主側が店舗営業をできなくなることによる損害が大きく、貸主側が提示した211万円の立ち退き料を考慮しても正当な事由にあたらないと判断され、立ち退きを認めませんでした。
>> 参照元:息子夫婦の付添い看護を受ける必要性(東京地裁昭和53年8月29日)
判例2:建物の経年劣化によるビル建築のための取り壊しの必要性に伴う立ち退き事案
貸主側が計画しているビルの建築のためには、経年劣化している建物を取り壊すことが必要であるとして、立ち退きを求めました。
このケースでは、建物に経年劣化が認められるものの、借主側が建物で10年以上にわたり焼肉店を経営して一定の利益を計上しており、テナントを退去することになれば生活に多大な影響があることや、建物の代替物件の確保が困難、店舗の移転による利益の維持は困難であること、また、経年劣化は建物の利用に大きな障害をきたすものではないという事情から、貸主側が提示した立ち退き料300万円では正当な事由にあたらないと判断され、立ち退きを認めませんでした。
>> 参照元:建物の経年劣化によるビル建築のための取り壊しの必要性に伴う立ち退き事案
立ち退き料の相場
テナントの立ち退き料の相場は、業種や立地などによって異なります。
詳しくは以下の関連記事で解説しておりますので、ぜひご一読下さい。
立ち退き料の補償金
テナント立ち退き料の補償金は、一般的に「転居に伴う移転費用の補償」、「営業補償」、「借家権価格の補償」の3つの補償が考慮されます。
詳しくは以下の関連記事で解説しておりますので、ぜひご一読下さい。
立ち退き交渉の進め方
テナントの立ち退き交渉は、以下の6ステップで進めます。
①貸主が立ち退きを求める理由を説明する
②借主の事情を傾聴する
③立ち退き時期や立ち退き料と敷金について交渉する
④譲歩できるポイントを考える
⑤書面で解決案を提示する
⑥交渉決裂した場合の代替策も考えておく
テナントの立ち退き交渉は、感情的にならず、双方が歩み寄りながら譲歩できるポイントを考えましょう。
そうすることで、納得のいく結果を得ることができます。
立ち退きの通知は6ヶ月までに!
テナント立ち退きの通知は、「解約の6ヶ月前までに通知をしなければならない」と借地借家法第27条で定められています。
貸主が6ヶ月より短い期間で立ち退きを要求しても、借主がその要求に従う義務はないため、貸主の計画した通りに立ち退きが中々進まないかもしれません。
そのため、立ち退きを要求する場合は、なるべく早い段階で立ち退きの通知を送付し、借主に立ち退きの準備期間を十分に与える必要があるため注意しましょう。
テナント・オーナー別|立ち退きの交渉ポイント
テナントやオーナーが立ち退き交渉を円滑に進めるためには交渉ポイントを考慮する必要があります。
テナント側・オーナー側がそれぞれ立ち退き交渉をする際のポイントについて以下で紹介しているため、ぜひご一読ください。
テナント側の交渉ポイント
テナント側が立ち退き交渉をする際に考慮すると良いポイントは以下の通りです。
| テナント側の交渉ポイント | ・費用の請求を行う ・移転先の見積もりを取る ・弁護士に相談する |
〇〇な立ち退き交渉は違法になる恐れも!
立ち退き交渉で違法になる行動は以下が挙げられます。
・手続きを踏まない強制的な交渉
・圧力や脅迫行為による交渉
・差別的な理由による交渉
こういった立ち退きを迫ってしまうと、法律違反となり、刑事罰や損害賠償を請求されるといった重大な法的責任が生じる結果となってしまいます。
オーナー側の交渉ポイント
オーナー側が立ち退き交渉をする際に考慮すると良い交渉ポイントは以下の通りです。
| オーナー側の交渉ポイント | ・早めに交渉を始める ・テナントの事情を把握する ・文書による条件提示 ・テナントの移転先の情報提供 |
立ち退き交渉が決裂した場合
テナントの立ち退き交渉が決裂した場合、貸主が立ち退き請求を断念して現状の賃貸借契約が継続するケースがほとんどです。
立ち退き料の支払いはないものの、借主側としては、テナントをこれまで通り賃料を支払いながら営業を続けることができます。
しかし、貸主側が「どうしても立ち退きをしてもらわないと困る」などで交渉が決裂した場合、調停や裁判所への訴訟に発展するケースもあります。
調停は、裁判所職員や有識者など第三者を介して引き続き交渉することを意味します。
調停の場合、あくまで双方の話し合いによりお互いが合意することで解決を図りますが、調停でも解決が見込めない場合、裁判にて交渉の決着をつけることになります。
立ち退き料の税務申告は?
テナントの立ち退きに伴い立ち退き料を受け取った場合は、確定申告が必要で、管轄の税務署に所得税を納税する必要があります。
また、所得税以外に課税対象となる税金が発生する場合があるため注意しましょう。
まとめ|「立ち退き」は場合によって認められる
テナントの立ち退きは、借地借家法に基づいた正当事由であると判断された場合に認められます。
正当な事由は、貸主側・借主側の事情、テナント契約に関するこれまでの経緯や経過期間、テナントの利用状況、立ち退き料が適切な金額であるかが条件となり、この条件を満たさない場合は正当な事由にあたらないとして立ち退きの要求に応じる必要はありません。
また、手続きを踏まない強引な交渉や、圧力や脅迫行為による交渉、差別的な理由による交渉は法律違反となり、刑事罰や損害賠償を請求されるといった重大な法定責任が生じてしまうため、立ち退きを求める際は、適切な方法で交渉を行いましょう。