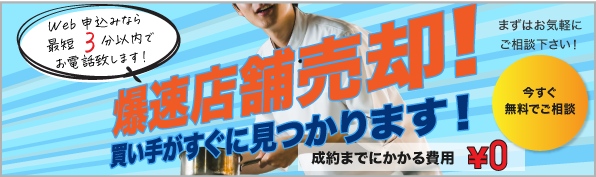テナントの立ち退き問題は、貸主と借主双方にとって非常にデリケートなテーマです。
特に、立ち退き料の金額をめぐる交渉は、裁判に発展するケースも多く、法律の知識や判例を押さえておくことが重要です。
この記事では、立ち退き料の相場をはじめ、算出方法や立ち退き料の税務申告から判例についてご紹介します。 トラブルを避けながら円満な解決を目指すためにも、ぜひ参考にしてください。
テナントの立ち退きとは
テナントの立ち退きとは、賃貸借契約において、物件の貸主(オーナー)が借主(テナント)に対して契約期間の更新拒絶や解約申入れを行い、物件からの退去を要求することを指します。
テナントに対して立ち退きを請求する際には、正当な事由が必要で、正当な事由がない場合は立ち退きを要求することができません。
また、立ち退きを請求する場合、契約期間満了の1年~6か月前に借主に通知して交渉を開始する必要があります。
立ち退き請求の正当な事由の例としては、主に以下のようなものがあります。
・建物の老朽化や災害により倒壊のおそれがある
・貸主やその家族の都合により物件に居住する必要がある
・都市再開発事業の計画がある
・借主が契約違反をしている
・借主が家賃滞納を繰り返している
・借主が近隣のテナントや住民に対して騒音や悪臭、嫌がらせなどの迷惑行為をしている
テナントの立ち退き料とは?建て替え時にも必要!?
テナントの立ち退き料とは、貸主から借主に対して支払われる補償金のことを指します。
貸主側の正当な理由を補完するために、貸主から借主に対して金銭が支払われて立ち退きを認めるようになった背景から、立ち退き料と呼ばれるようになりました。
立ち退き料は建物の老朽化による建て替えなど貸主都合による退去で発生するケースがありますが、立ち退きの事由や状況によって異なります。
立ち退き料の算出方法
立ち退き料は、以下の3つの要素を合計した額として算出されることが多いです。
1.新店舗への移転費用
2.移転により生じる減益・減収についての営業補償
3.借地権価格(借主としての地位自体に認められる財産的価値)
新店舗への移転費用の内訳は、主に以下の6つです。
1.現在の店舗との家賃の差額についての補償
2.新店舗を借りる際の敷金・礼金等
3.新店舗を借りる際に必要になる仲介手数料
4.新店舗の内装費用
5.引っ越し費用
6.新店舗への移転を顧客に案内するための広告・宣伝費用
次に、移転により生じる減益・減収についての営業補償の内訳は、主に以下の3つです。
1.移転期間中に失われた営業利益に対する補償
2.移転期間中に支払いが必要な固定費や従業員の休業手当に対する補償
3.店舗移転により顧客を失うことが予想される場合の損失補償
最後に、借地権価格については、立ち退き料の計算に入れていない裁判例も多く、必ず立ち退き料の計算に組み込まれているわけではありません。
立ち退き料の算出に入れる場合もその金額の決め方は、裁判例により異なるため注意しましょう。
立ち退き料は課税対象?
貸主側から補償金としてもらう立ち退き料は借主の所得となるため、確定申告が必要です。
課税対象となる種類は以下の3つになり、税率は所得額に応じて5〜45%まで設定されています。
・資産消滅の大家補償となる場合:譲渡所得
・店舗の営業補償となる場合:事業所得
・その他の理由で立ち退き料を受け取る場合:一時所得
法人が立ち退き料を受け取った際は益金に計上し、法人税の課税対象となります。 なお、立ち退き料は消費税の課税対象となりませんので注意しましょう。
立ち退き料の補償金
立ち退き料には、一般的にテナントの移転により生じる可能性のある営業上の利益に対する補償金として営業補償が含まれています。
この営業補償は「営業休止補償」と「営業廃止補償」に分けられます。
営業休止補償とは、立ち退きにより新たなテナントで営業をする場合の補償、営業廃止補償とは、立ち退きにより廃業等に伴う補償のことを指します。
営業補償として考慮されるポイントは、以下の3つです。
・休業期間中の営業利益
・休業期間にかかる固定費
・常連顧客を失う可能性があると想定できるか
休業期間中の営業利益については、移転期間中に新たな移転先が見つかったとしても、移転には内装や外装の工事などで一定の期間が必要です。
そのため、その間に得られる予定であった利益については営業補償の範囲となります。
次に、休業期間にかかる固定費などについてです。
雇用している従業員は解雇せずに移転先でも働いてもらいたいと考えるでしょう。
そのため、休業期間に発生する給料は休業補償として従業員に支払います。
また、移転先のテナントを借りれば敷金礼金や仲介手数料、毎月の賃料など固定費の負担があるため、立ち退きがなければ本来かからない金銭についても、営業補償として考慮されます。
最後に、常連顧客を失う可能性があると想定できる場合についてです。
移転先の店舗が同じ町区内であるなど、比較的近隣への移転であれば常連顧客を失うことはないですが、一方で、移転先が隣町や数キロ離れた地域であれば、近隣の常連顧客は足が遠のく可能性があります。
長年通う顔馴染みの常連顧客であれば、頻繁に利用するケースもあるでしょう。
しかし、移転先の店舗が生活圏外であれば、来店する回数は減少する可能性が高くなります。 そのため、常連顧客の足が遠のくような立地への移転を余儀なくされれば、営業補償として考慮されるポイントとなります。
業種別立ち退き料の相場
一般的な立ち退き料の相場は賃料の2〜3年分程度です。
テナント物件からの立ち退きでは、居住用として利用されている場合と比べ、支払われる立ち退き料が高額になる傾向があります。
また、裁判に発展するケースでは一般的な相場の約5倍と一気に跳ね上がり、賃料10万円の店舗の立ち退き料は、1,000〜1,500万円程度となる判例が多いです。
以下の業種別で詳しく解説します。
・美容室の立ち退き料の相場
・飲食店の立ち退き料の相場
美容室の立ち退き料の相場
美容室の立ち退き料の相場は、一般的に800〜3,000万円程度です。
この立ち退き料には、以下の要素が含まれています。
・移転費用:引っ越し費用や新しい店舗の内装費、保証金、移転案内の広告費用など
・営業補償:移転に伴う休業期間中の売り上げ損失や、常連顧客を失う事による売り上げ減少の補填
・借地権の補償:借地権の価値に対する補償
この要素を総合的に考慮して立ち退き料が算出されます。 具体的な立ち退き料の金額は、店舗の立地や規模、営業状況、賃貸借契約の内容などによって異なるため、専門家への相談をおすすめします。
飲食店の立ち退き料の相場
飲食店の立ち退き料の相場は、一般的に1,000〜1,500万円程度です。
例えば、賃料が30万円の店舗であれば、1,000〜2,000万円が目安となります。
立ち退き料の金額は、賃料を基準としますが、立地への依存度や現在の売上・利益の額によっても変動します。
また、店舗の立ち退きには引っ越し費用や新しい店舗の内装費、保証金、移転案内の広告費用など多額の費用がかかるため、立ち退き料が高額になる傾向にあります。
テナント家賃別立ち退き料の相場
テナント家賃別立ち退き料の相場は一般的に賃料の6〜15ヶ月分程度です。
ただし、具体的な金額は店舗の立地や規模、営業状況、賃貸借契約の内容などによって異なります。
・家賃10万:60〜150万円
・家賃30万:180〜450万円
・家賃50万:300〜750万円 テナント家賃別立ち退き料の相場はあくまでも目安です。
もし立ち退き交渉を行う場合は、専門家へ相談すると、適切な条件で交渉を進めることができるでしょう。
立ち退き料の判例
立ち退き料の判例は、立地、建物の老朽化、賃料、営業内容など多様な要素が考慮され、立ち退き料の金額決定となります。
以下の通りです。
・判例1:専門学校の立ち退き事案
・判例2:ピアノ教室の立ち退き事案
詳しく解説します。
判例1:専門学校の立ち退き事案
専門学校に貸していた建物は、築年数が35年経過しており、雨漏りが発生し、防災関係においても問題があるなど状態が悪く、建物を取り壊して、建て直すために2,640万円を支払うとし立ち退きを要求しました。
裁判所は、建物の老朽化が激しいため、貸主が立ち退きを要求することは正当な理由であると判断しました。
裁判所の判断に基づく立ち退き料は、借主が専門学校の運営を継続する必要性が高いが、移転による営業利益の損失、移転にかかる費用などの補償が必要との判断を下しました。
結果、2,640万円から4,000万円への1,460万円の増額により立ち退きを認めました。
判例2:ピアノ教室の立ち退き事案
借主がピアノ教室を行っていた建物は、築年数が65年ほど経過しており、大きな地震が発生した場合には倒壊する可能性が高く、立ち退き料170万円を支払うとし立ち退きを要求しました。
裁判所は、借主は高齢でピアノ教室での指導のみで生計を立てており、転居先となる物件が見つからない上、貸主が提示した立ち退き料が170万円と少額だったことから、170万円では正当な理由を補完する役割を果たさないとし、立ち退きを認めませんでした。
立ち退き料の税務申告は?
テナントの立ち退き料は税務申告が必要です。
立ち退き料を受け取った場合と、支払った場合それぞれが行う必要のある税務申告について解説します。
■立ち退き料を受け取った場合(借主側)
立ち退き料は、税務上「収入」とみなされ、課税対象になります。
ただし、受け取る立ち退き料の性質によって課税の種類が異なります。
【営業補償の場合】
・所得区分:事業所得または雑所得
・課税対象:営業の損失補償として受け取る立ち退き料は、収入として申告が必要です。
・経費計上:実際に支出した移転費用や営業再開のための費用を必要経費として計上しましょう。
【賃借権の譲渡補償の場合】
・所得区分:譲渡所得
・課税対象:借地権や賃借権の価値を補償する立ち退き料は「譲渡所得」として扱われます。
・経費計上:賃借権の取得費や立ち退きに関連する経費を譲渡所得として計上しましょう。
■立ち退き料を支払った場合(貸主側)
立ち退き料を支払った側も、税務上の取り扱いが発生します。
立ち退き料を支払った場合は、経費として計上しましょう。
立ち退き料の支出目的:営業活動を継続するための必要経費として認められる場合、法人税や所得税の計算上、全額を損金または必要経費に計上することが可能です。
ただし、支払った立ち退き料が高額と判断された場合、全額が経費として認められない可能性があるため注意しましょう。
まとめ|最適な立ち退き料を設定しましょう
テナントの立ち退きは、建物の老朽化、都市再開発、借主の契約違反、家賃滞納などが該当し、立ち退きを要求することが可能です。
立ち退き料の相場は一般的に賃料の2〜3年分程度ですが、具体的な立ち退き料の金額は、店舗の立地や規模、営業状況、賃貸借契約の内容などによって異なります。
また、貸主が借主に対して支払った立ち退き料が高額と判断された場合、全額が経費として認められない可能性があるため、専門家に相談した上で、最適な立ち退き料を設定しましょう。