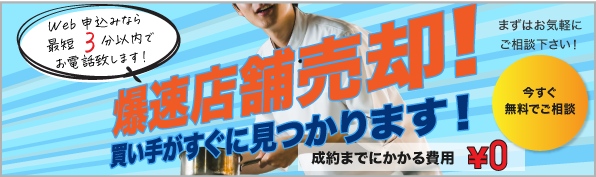固定資産税は、土地や不動産を所有している人が納めるものだと思っている人も多いのではないでしょうか。
実際は、土地や不動産だけでなく、テナントを借りて店舗やオフィスを経営している人も固定資産税の課税対象となるケースもあります。
今回は、テナントの固定資産税とは何か・減額はできないのかをはじめ、内装工事に固定資産税はかかるのか、固定資産税が免除されるケースなどテナント側の固定資産税について詳しく紹介します。
テナントの固定資産税とは?減額はできない?
固定資産税とは、不動産や取得価額が10万円以上の車両、備品・什器類などの償却資産を所有している限り毎年市町村に納める地方税のひとつです。
パソコン、コピー機、椅子、机、ロッカーや厨房機器等の自らの事業に使用するために購入した備品・什器類や、電気・ガス・給排水設備、内装工事費といった法人税法や所得税法などに基づき減価償却費として経費計上できるすべての償却資産が固定資産税の課税対象となります。
また、固定資産税は以下のようなケースに該当する場合、管轄の自治体に申請することで減額をすることができます。
・耐震改修工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事を実施した
・中小企業や特定の業界を対象とした特例措置を利用する
・耐用年数を見直して償却資産の正確な申告を行う
・自然災害等で被害を受けた
以下より詳しく解説します。
内装工事に固定資産税はかかる?
固定資産税の課税対象は、内装工事を行い減価償却として会計処理を行なったすべての工事が対象となり、テナント入居している店舗やオフィスを内装工事した場合にも固定資産税(償却資産税)がかかります。
内装工事費は一度に経費にすることはできないため、決められた使用期間にわたって分割し、減価償却を行う必要があります。
内装工事費の減価償却として会計処理を行う対象となる工事例は、建物や建物付属設備に関するすべての工事、固定資産価値を高める改修工事です。
減価償却は資本的支出となり固定資産とみなされるため、固定資産税の対象となります。
固定資産税の計算方法
固定資産税の計算方法は、課税標準額×税率という方法で計算されます。
課税標準額や税率によって異なりますが、課税標準額150万円、税率1.4%の場合は、
例:課税標準額150万円×税率1.4%=21,000円
という計算方法になり、固定資産税を21,000円納税するということになります。
固定資産税の税率は基本的に1.4%ですが、償却資産を管轄する自治体によって1.5%や1.6%など税率に若干の差がありますので、気になる場合は、テナントを借りている地域の固定資産税率を確認しておきましょう。
固定資産税が免除されるケース
固定資産税が免除されるケースはいくつかあります。それぞれ詳しく解説します。
ケース1:固定資産税が合計課税標準額を満たさない場合
ケース2:公共施設等に指定されている場合
ケース3:自然災害等の被害を受けた場合
固定資産税が免除されるケースの場合、自身が該当するか正しく把握し上手に活用することで節税することが可能です。
ケース1:固定資産税が合計課税標準額を満たさない場合
固定資産税が合計課税標準額を以下の基準を満たさない場合は固定資産税が免除されます。
・土地:30万円未満
・家屋:20万円未満
・償却資産:150万円未満
ただし、同じ市町村内に複数の土地や建物を所有している場合は、合計額で判断されます。
ケース2:公共施設等に指定されている場合
学校や福祉施設、公園、公衆用道路などの国、地方公共団体や学校法人、社会福祉法人などが所有している公共施設等に指定されている場合は固定資産税が免除されます。
ケース3:自然災害等の被害を受けた場合
地震や台風などの自然災害等の被害を受けた場合は、固定資産税が免除されます。
全額免除となるケースは、火災や地震により建物が全壊・全焼など原型を留めずに修復不能となり、納税期限が被災日以降で納税していない固定資産税が免除の対象となります。
まとめ|固定資産税に気を付けましょう
固定資産税は、不動産を所有している人だけでなく、一定額以上の償却資産を所有している人も納税義務が発生する税金です。
固定資産税の課税標準額は、国単位ではなく全国各地の地方自治体が独自に調査した上で行っており、場合によっては、自治体の評価や計算方法に誤りが生じている可能性があるため、本来支払う必要のない税金まで支払っていないか疑問に思われる方は、自治体に確認してみましょう。