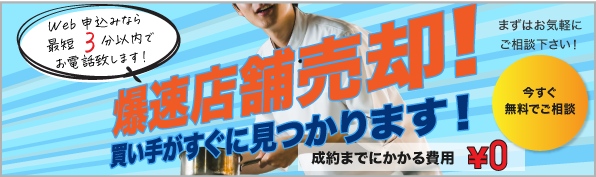店舗やオフィスの運営費用のひとつである電気代。
営業時間や規模が大きければ大きいほど、電気代の負担も増しますが、テナント用物件の電気代がどのように決まっているのかご存知でしょうか?
この記事では、テナント用物件の電気代の決まり方、電気代の基本料金や電気代のインボイス制度・消費税とは何か、電気代の上乗せは違法なのか、電気代の節約方法についても解説します。
テナント用物件の電気代の決まり方
テナント用物件の電気代の決まり方は、店舗が多数ある商業ビルなどの規模や構造により異なります。
大規模なオフィスビルや商業ビル等では、ビルの所有者が高圧電気の一括契約を締結しているのが一般的です。
ですが、テナント物件ごとに設けたメーターを利用して電気代を割り出して個別に請求を行う一括契約は、テナント側が電気料金の内訳を確認することはできないため注意が必要です。
一方、マンションの一室をオフィスとして利用している場合や単独店舗、小さな雑居ビル等の場合は、一般の住宅と同じように、各テナントがそれぞれ選んだ電力会社と個別契約をすることが多いです。
電力会社や業務用プランの中から自分のテナントの形態に合わせた契約を選べ、契約内容がテナントごとに確認できるため、節電をすれば電気料金を抑えることも可能です。
電気代の基本料金
電気代のもととなる基本料金は、ビル全体で使用される電力量を計測し、1日の中で最も使用量の高い30分間の値(最大需要電力)によって決まります。
適用されている最大需要電力を超過すると、契約電力が上がり、超過した月から1年間はこれまでよりも高額な電気料金を支払う仕組みとなっています。
そのため、最大需要電力を超過し基本料金が上がれば、その分、テナント側の負担額も増加してしまうため注意が必要です。
テナントビルの電気代単価
テナントビルの電気代単価は契約内容やテナントの規模、電気の使用量により異なります。
大規模なオフィスビルやショッピングセンターなどの商業ビル等が電気会社と契約している一括契約では、1kwあたりの基本料金と従量料金は個別契約よりも割安になる傾向があり、昨今の電気代事情を踏まえると20~35円/kWhといわれています。(参考:北海道電力_「業務用電力」)
テナント用物件の電気代の計算方法
電気代の計算方法は、契約している電力会社の契約プランや電力使用量に基づいて計算されるのが一般的で、基本料金+電力量料金+再生可能エネルギー発電促進賦課金=合計電気代という方法で計算されます。
具体的な料金は、契約内容や電力会社によって異なるため、電力会社の料金表や請求書を確認するようにしましょう。
電気代のインボイス制度・消費税とは
電気代のインボイス制度・消費税とは、事業者が電力会社から受け取る適格請求書(インボイス)を管理し、経費として適切に計上するための制度です。
インボイス制度開始後、売手の登録事業者は、取引相手に応じて適格請求書(インボイス)の交付が義務付けられます。
そして、仕入税控除の適用を受けるために、買手は取引相手である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存が必要となります。
インボイス制度による電気代
インボイス制度開始前は、ビルのオーナーからの電気代請求書に基づいて支払うことで何も問題ありませんでした。
ですが、インボイス制度開始後、電気代はテナント宛の請求書ではないため、電気代に対する消費税相当分がテナント側の負担として増えることになり、立替金精算書だけでは経費計上することができなくなります。
これを避けるためには、ビルのオーナーは、電力会社の請求書をコピーしたものと立替金精算書をセットでテナントに発行することで、インボイス制度前と同様の経理処理が可能になります。
また、インボイス制度による電気代の適応範囲には、基本料金、従量料金、燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金などの電気を使用する際に発生する全ての料金が含まれます。
これにより、電気代の内訳を把握することができ、電気代の透明性と正確性を確保し、適切な経理処理を行うことができます。
電気代の消費税対象
| 課税対象 | 非課税 |
| ・基本料金 ・従量料金 ・燃料費調整額 ・再生可能エネルギー発電促進賦課金 | ・非課税なし |
電気代は簡易課税?
電気代は消費税法上、課税仕入れに該当し、簡易課税制度において簡易課税に区分されるものではありません。
電気代は通常の経費として計上されるものであり、消費税率は10%が適用されます。
電気代の上乗せは違法?判例も紹介
一括契約や高圧受電は個別契約よりも電気代が安くなる傾向があります。
本来ならば安いはずの一括受電や高圧受電で、オーナーや家主から電気代の高額請求が届いてしまったという経験をしたことはありませんか?
ここからは、電気代の上乗せとは一体何なのか、電気代の上乗せの判例についてご紹介します。
電気代の上乗せに困っている方は、ぜひご一読ください。
電気代の上乗せとは
電気代の上乗せとは、基本的な電気料金に加えて追加で課される費用のことを指します。
「契約書に記載されていない内容を補充するもの」という意味合いで、テナントはビルオーナーや家主に異議を述べずに電気料金を支払うという商習慣が存在すると言われており、半ば慣習として行われてきました。
電気代の上乗せが起きる理由は、キュービクルと呼ばれる高圧受電をするために欠かせない変圧器を利用しているからです。
キュービクルの設置には初期費用として数百万円がかかり、毎月の維持費に数万円がかかります。
さらに、部品を交換する際に100万円近くする部品も存在するため、こういった諸経費の補填として上乗せが起きるといえます。
電気代の上乗せは、慣習として行われてきましたが、東京地裁では「上乗せを商慣習とするのは認められない」、札幌高裁では「実費以上の電気料金を請求するのは違法」との判決が下されており、法律上電気代の上乗せは違法となります。
電気代上乗せの判例
電気代の上乗せの判例について2つの例を挙げて解説します。
判例1:宮崎県宮崎市のテナントビルに入居する企業が「実質より高い電気料金を請求された」として貸主に対して過払金の返還を求めた訴訟で、東京地裁が実費を超えて支払った約257万円の返還を命じました。
判例2:北海道札幌市薄野の飲食店が「実費の2倍近い電気料金を支払わされた」として貸主に返還を求めた訴訟では、最高裁が貸主側の上告を棄却し、約1020万円の支払いを命じました。
上記の判例で共通する貸主側の主張は、「商慣習に基づいているから合法」「設備の維持管理費だから合法」「借主側が何も言っておらず黙示の合意をした」というものです。
しかし、いずれの主張も法的に通じないため、返還請求はできると考えられます。
電気代の請求方法
電気代の請求方法は、一括契約と個別契約の契約形態によって異なります。
一括契約の場合は、ビルのオーナーが一括でビル全体の電気料金を支払い、その後、個別でテナントごとに電気代を請求する方法になります。
個別契約の場合は、一般家庭と同様に各テナントで電気契約を行い、個別で電力会社に支払う方法になります。
電気代の請求方法は、ビルによってあらかじめ決定しているため、一括契約のビルに入居しているにも関わらず、個別契約の方法で電気代を支払うことはできませんので注意しましょう。
テナントによる電気代の節電方法
テナントによる電気代の節電方法は一括契約と個別契約の契約形態によって異なります。
一括契約の節電方法は、他のテナントに節電するようアナウンスを求めたり、施設管理者に共用設備のLED化や省エネ型セントラル空調への切り替えを求めるといった意見を挙げることです。
長くテナントを利用する予定があるなら、積極的に施設管理者に働きかけたり、他のテナントと協力し合うことも考える必要があります。
個別契約の節電方法は、新電力への切り替えやすでに契約している電力会社で、電気代がさらに安くなるプランがないかシミュレーションをするといった方法です。
近年、電気単体だけでなく、ネット回線や他のサービスと組み合わせることで電気代が節約できるプランが登場しているため、検討してみると良いでしょう。
一般的に個人でできる節電方法は以下のとおりです。
・空調のフィルター掃除
・扇風機やサーキュレーターで空気を循環させる
・照明をLEDに変更する
以下でそれぞれ解説します。
空調のフィルターを掃除する
空調のフィルターが汚れたままだと、冷暖房の効率が落ちてしまいます。
定期的に空調のフィルターを掃除することで、冷暖房効率を上げることができます。
その結果、電気代節約につながります。
扇風機やサーキュレーターで空気を循環させる
扇風機やサーキュレーターで空気を循環させることで、室内温度にムラがなくなり、必要以上にエアコンの温度を下げなくても快適に過ごせます。
扇風機やサーキュレーターは電気代が安いため、エアコンと組み合わせて使用することで、電気代節約につながります。
照明をLEDに変更する
照明をLEDに変更することで消費電力を大きく削減することができます。
LEDは蛍光灯や白熱灯と比べて商品価格は高いですが、長期的な節約効果が高いというメリットがあります。
また、照明の寿命も長いため、買い替えや付け替えのコスト削減にもつながります。
まとめ|電気代の上乗せには気を付けましょう
電気代は毎月かかる経費なだけに、できるだけ節約したいと考える方も多いでしょう。
電気代を上乗せされるのは法律上、違法になりますが、契約書に「オーナーや家主が妥当だと判断する方法で算出した金額を支払う」旨の記載がある場合は、過払金を請求できない可能性があります。
裁判所への訴訟はあくまでも最終手段なので、「一度オーナーや家主としっかりと話し合う」若しくは「弁護士に相談する」という手段を取るようにしましょう。